亡くなった親の家を片付ける手順を紹介!片付けを効率よく実施するためのポイントは?
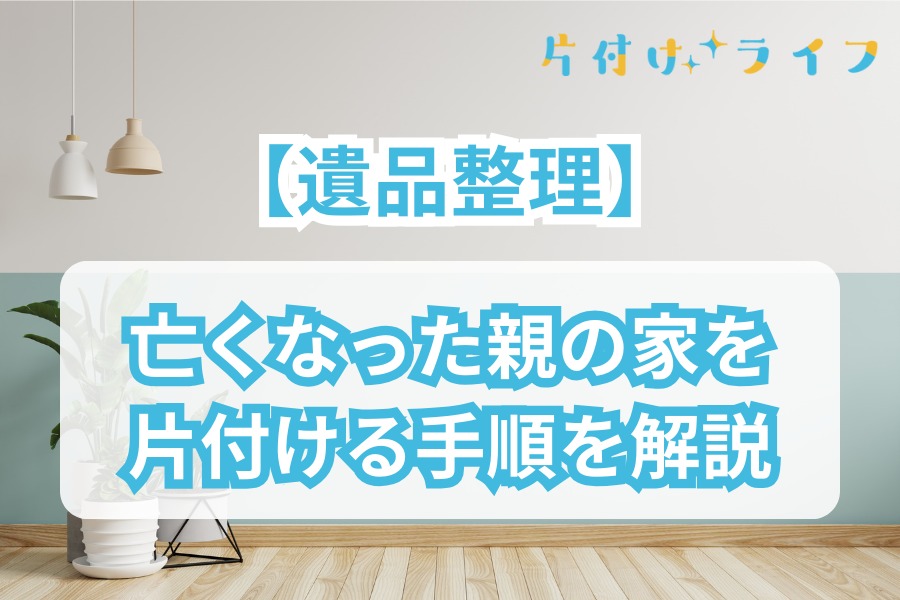
実家を離れて住んでいて、実家に住んでいる親が亡くなった場合、片付けが必要になる場合があります。
また、配偶者の親が亡くなって家の片付けを手伝うケースもあるでしょう。
この際に、どのように片付けすればよいのか悩むものです。
では、実際に亡くなった親の家をどのように片付ければ良いのでしょうか?
本記事では、片付けを効率よく実施するためのポイントや、片付ける際の注意点などを紹介します。
片付けをどのようタイミング実施すればよい?

親の家を片付ける際に、どのタイミングで片付けすれば良いのか悩むものです。
親が亡くなった後に、葬儀の準備を進めると同時に、様々な手続きをおこなう必要があります。
よって、片付けしている時間が取れないケースが多いです。
ただし、そのまま放置しておくわけにはいかず、片付けを進める必要があります。
正確には、いつまでに片付けを完了させなければならないというルールは存在しません。
一般的には、残したものを形見分けする場合が多く、形見分けするためには親族などが集まるタイミングが最適です。
そこで、四十九日法要までにある程度の片付けをおこなっておくのが良いでしょう。
また、故人が残したものを相続する必要がありますが、遅くとも相続をおこなうまでには完了させなければなりません。
以上を加味して、無理しない程度で片付けを進めることをおすすめします。
実家の片付けをおこなう際にチェックしたいポイント

実家の片付けをおこなう際に、何も考えず片付けすると失敗する場合が多いです。
以下の項目をよく確認して、後でトラブルが発生しないように注意しなければなりません。
- 遺言書やエンディングノートの有無を確認する
- 誰が相続人となるのかを確認する
- 財産を確認する
- 形見分けする必要があるものがあるかを確認する
各注意点について、詳しく解説します。
遺言書やエンディングノートの有無を確認する
親の家を片付ける際には、相続すべきものの有無を事前によく確認しておく必要があります。
また、相続以外にも故人から残してほしいものがリクエストされている場合があります。
そこで、遺言書が残されているかどうか、遺言書がある場合は相続に関する記載があるかを確認してください。
遺言書には法的効力があるため、記載された内容を必ず遵守しなければなりません。
よって、真っ先に遺言書の内容を確認して相続に関する希望の有無を確認してください。
同時に、法的効力はないもののエンディングノートに相続や遺品整理に関する希望が残されているかを確認しましょう。
エンディングノートの場合、遺言書のように細かなルールはなく、気軽に作成できるメリットがあります。
よって、遺言書以上に細かな希望が残されている場合があるため、よく内容を確認してください。
誰が相続人となるのかを確認する
遺言書に相続人に関する記載があれば、それに従って相続人が決定されます。
ただし、必ずしも遺言書に記載されているわけではなく、相続に関する事柄がない場合もあります。
その場合、法律上で相続人が誰になるのかを調べなければなりません。
相続人調査を実施する上で、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を入手する必要があります。
身内であれば関係性が明らかであり、誰が相続人となるのかを容易に把握できます。
ただし、他人から見た場合に家族関係を客観的に証明するための証拠が必要となるのです。
よって、相続人調査を実施して実証する作業が必要となります。
特に、遺産分割協議を実施する際には相続人全員の参加をもって実施しなければならず、相続人の把握はとても重要な作業です。
財産を確認する
相続を進める上で、故人がどのような財産を保有しているかを確認する必要があります。
故人が生前整理として財産目録を作成していると、容易に財産の状況を確認可能です。
もし作成していない場合は、どのような財産を保有しているのかを自分で確認しなければなりません。
なお、ここで言う財産とは、プラスの財産だけでなく負債や借入などマイナスの財産も把握する必要があります。
形見分けする必要があるものがあるかを確認する
親の家を片付ける際には、相続だけでなく形見分けを意識して実施する必要があります。
形見分けとは、故人の親族や親交のある方に対して遺品を贈って、思い出を分かち合うという日本に古くから伝わる風習です。
形見分けは、基本的に相手側から贈って欲しいという希望がある場合、それに応じておこなう形となります。
形見分けする際には、贈与税の対象となるのかどうかをよく確認しておこなう必要があります。
また、渡す際には包装しないのがマナーであり、こちらから無理して渡すものではありません。
上記に注意して、遺品整理を実施する中で形見分けすべきものがあるかを確認してください。
親の家を片付ける手順

亡くなった親の家を片付ける際には、以下の手順で進めましょう。
- 貴重品や重要書類を捜索する
- 範囲を明確にして順序よく片付ける
- 分別作業をおこなう
各ステップについて、詳しく解説します。
貴重品や重要書類を捜索する
親の家を片付ける際には、相続を強く意識して実施しなければなりません。
そこで、貴重品や重要書類などを探す作業が必要です。
故人がエンディングノートなどで保管場所を指定している場合があるため、事前に内容をよく確認しておきましょう。
単純に価値が高いという観点ではなく、相続の観点で実施することをおすすめします。
棚や引き出しの中だけでなく、タンスや額縁の裏などに隠すように保管されている場合もあるため、隅々まで確認しましょう。
範囲を明確にして順序よく片付ける
貴重品などの捜索が一段落したら、本格的な片付け作業に入ります。
一度に家の中を全て片付けるのは困難であり、エリアを決めて愚直に対応する必要があります。
また、家具など重いものを運ばなければならない場合もあるため、親族に手伝ってもらいながら進める方法が有効的です。
その場合、作業を始める前にどの範囲をどのように片付けるのかを事前に決定しておきましょう。
分別作業をおこなう
片付けを進めると同時に、残すものと不要なものを仕分ける作業が必要です。
残すものについては、家にそのまま残すものと相続や形見分けが必要なものに分類しなければなりません。
また、不要なものはゴミとして処分するのか買取してもらうかなどの観点で分別していきます。
残すものと不要なものを判断する場合、故人の遺志だけでなく親族の意見も取り入れて作業すると、後でトラブルに発展するリスクを回避できます。
親の家を効率よく片付けるためのコツ

親の家を効率よく片付けるためには、以下のような点を意識してください。
- 事前にスケジュールを明確にする
- 仕分けるスペースを確保する
- 残すべきか悩むものは一旦保留する
- 遺品整理業者に作業を依頼する
各コツの詳細は、以下のとおりです。
事前にスケジュールを明確にする
家の片付けをする場合、時間がかかるケースが多いです。
そこで、事前にどの程度時間がかかるのかを把握して、スケジュールを立てて計画的に実施する必要があります。
また、親族が集まって作業する場合は、集まりやすいタイミングを見計らってスケジューリングできるかがポイントです。
スケジュールを立てて、親族と共有して効率よく実施しましょう。
スケジュールを立てる際には、自治体のごみ収集日に合わせるのも良いでしょう。
仕分けるスペースを確保する
遺品の仕分けをおこなう際には、作業スペースを確保する必要があります。
また、仕分けた後に処分すると判断したものについて、処分するまで一時置きするスペースの確保も必要です。
よって、片付け作業の最初の段階で作業スペースを確保してください。
残すべきか悩むものは一旦保留する
家の片付けにより、処分するべきかどうか悩むものが多数存在します。
特に、故人との思い出の品となるものは、そう簡単に処分できないものです。
思い切って処分してしまい、後で後悔するケースもあるため慎重な判断が必要です。
そこで、処分すべきかどうかを判断できないものは、一旦判断を保留して残しておくと良いでしょう。
そして、親族などの意見を取り入れて後日改めて判断する対応がおすすめです。
遺品整理業者に作業を依頼する
家の片付けは力仕事となり、危険が伴うものです。
また、不要と判断したものを処分するために、別途トラックなどを準備しなければならない場合もあります。
自分ひとりで準備するのは大変であり、費用もかかります。
そこで、遺品整理業者に依頼すれば手間をかけることなく家の片付けをおこなえるのでおすすめです。
遺品整理業者の場合、故人や依頼者の思いを汲んで遺品の仕分け作業から処分まで対応してもらえます。
また、業者によっては不当と判断した遺品の買取にも対応してもらえる場合もあります。
さらに、相続の相談にも応じてもらえるなどのサービスも提供している場合もあり、心強い存在です。
業者に依頼する場合は費用がかかるものの、費用対効果を考えれば十分検討の余地があると言えます。
まとめ

親が亡くなった後に、家を片付ける際には手間がかかる作業となります。
特に、多くのものが残っていて、部屋が多い家の場合は自分ひとりでは対応できないケースも多いです。
親族の協力を得たり、遺品整理業者に依頼したりして、無理なく片付け作業を進めましょう。
その遺品整理
片付けライフにお任せください!
豊富な経験と専門知識をもつプロの「遺品整理士」が丁寧に対応いたします。
優良事業所にも指定されておりますので、安心してご依頼ください。
片付けライフは出張費用や追加料金が一切かかりません。
もちろんお見積りも無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
